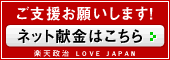› 宮崎政久(みやざきまさひさ)のオフィシャルブログです › 婚外子の相続格差違憲判決と保守の思想
› 宮崎政久(みやざきまさひさ)のオフィシャルブログです › 婚外子の相続格差違憲判決と保守の思想2013年09月11日
婚外子の相続格差違憲判決と保守の思想
先日、最高裁判所から、婚外子(結婚していない男女間に産まれた子)の相続格差に関する民法900条4号但書の規定が憲法違反であるとの判断が下されました。
10月15日開会予定の臨時国会でこの法律の改正が審議されるものと思います。
この判決に対し、「保守」と称する方々から「法の賢慮が負けた」などと疑問の声が出たり、法改正に後ろ向きのコメントが出されているようです。
今回は、保守の立場から、この問題に触れてみます。
まず、憲法違反と言われた規定は、どんな定めなのか。
これは「嫡出でない子の相続分は嫡出である子の相続分の2分の1」とされた規定です。
結婚した男女から生まれた子のことを「嫡出子」といい、タイトルにある「婚外子」のことは「非嫡出子」といいます。
例えば、男が妻との間の子がいて、妻以外の女性との間にも子がいて、この男性が亡くなったという場合、妻以外の女性との子は、妻との間の子の半分の相続権しか認められないということです。いわゆる本妻の子が優先されているのです。
子供は親を選べません。
最高裁もいうように、「父母が婚姻関係になかった」という、子供が自ら選ぶことができず、かつ自ら修正する余地のないことを理由として、子に不利益を及ぼすことは許されるべきではありません。
婚外子の立場からすれば、「自分は、父母が婚姻関係になかったというだけで、婚姻関係にあった子(異父母の兄弟)の半分の権利しかない。」となれば、そこに「正義」はありません。
よって、私も最高裁の判断は妥当と考えています。
ただ、単純な話で終わってはいけない。
この問題は、相続制度に関することであって、相続制度は、その国の伝統、社会事情、国民感情、婚姻や親子関係への意識や規律を総合的に考慮して法律によって制度が確立されるべき問題であって、「どの国でも通用する絶対的正義」が存在するわけではありません。
つまり、どんな相続制度の法律にするかは、その国ごとに裁量の幅が認められるものだということです(立法裁量といいます)。
この婚外子の相続格差は、もともと明治31年制定の民法で、当時の「家制度」を維持するため、婚外子も戸主となれることから、2分の1の権利を認めて制定されたもの。
敗戦後の民法改正でも「法律婚の尊重と婚外子の保護の調整」を図るために存続されたものです。
「家制度」に起因すると、それだけでヒステリーに反応する向きもありますが、制定時も敗戦後も、我が国の国家状況、国民意識等からして、認められて当然の規定です。
ちなみに、「人権、人権、平等、平等」と声の大きい欧米諸国では、キリスト教の影響から、もともとは婚外子には法的権利が認められていなかったのです。それが、1960年代になってから国際的な人権尊重の潮流が起き、婚外子の権利除外規定が撤廃されていった歴史があります。
ですから、我が国でも、もともとは国民意識として法律婚を尊重するために規定していたものですが、時代も進展し、子を個人として尊重し権利を保障すべきという考えが確立されてきたことで、現在では、このような婚外子の相続分に格差を設けるのはよろしくないと判断するに至ったと考えるべきです。
「もともと日本は悪かった」的な言説は論外です。
そのうえで、これは相続制度の問題であり、相続に関わるのは、「子」だけではありません。
相続に関与する「配偶者」、「嫡出子」、「非嫡出子(婚外子)」には、いずれにもそれぞれの「正義」があり、その「正義」は相互に矛盾をはらんでいます。
今回の最高裁の判断を受けて、嫡出子の側は「幸せな家庭を壊された上に、家から追い出された」とコメントしています。
仮に相続財産として家屋しかなかった場合、(嫡出子と同等の権利が認められる)婚外子からの請求を受けると、配偶者が老後の居住場所を失う可能性もあるわけです。
配偶者には、結婚をして共同で財産を形成して老後に備えてきたという「正義」がある。法律婚を守ってきたという「正義」がある。
今回の最高裁判断を受けて、法改正がされます。
私は、その際に、配偶者を手厚く保護するための配慮がされるべきだと考えています。
最高裁判決を受けた報道に接したとき
「我が国伝統の家族意識への危機が…」
とか
「法の賢慮が悪しき平等主義に負けた…」
などと保守派と称する方々から大上段に構えた意見がありましたが、私は必ずしも賛成しません。
私たち国民の意識にある「家族を大切にする思い」、「法律婚の尊重」は、様々な立場の「正義」との配慮とともに大切にされるべきです。
法律では、相続にあたって配偶者への手厚い配慮を規定するなどで、様々に「正義」への配慮が考えられるべきです。
保守であればこそです。
10月からの国会審議でも、単純化しない保守の議論を展開したいと考えています。
10月15日開会予定の臨時国会でこの法律の改正が審議されるものと思います。
この判決に対し、「保守」と称する方々から「法の賢慮が負けた」などと疑問の声が出たり、法改正に後ろ向きのコメントが出されているようです。
今回は、保守の立場から、この問題に触れてみます。
まず、憲法違反と言われた規定は、どんな定めなのか。
これは「嫡出でない子の相続分は嫡出である子の相続分の2分の1」とされた規定です。
結婚した男女から生まれた子のことを「嫡出子」といい、タイトルにある「婚外子」のことは「非嫡出子」といいます。
例えば、男が妻との間の子がいて、妻以外の女性との間にも子がいて、この男性が亡くなったという場合、妻以外の女性との子は、妻との間の子の半分の相続権しか認められないということです。いわゆる本妻の子が優先されているのです。
子供は親を選べません。
最高裁もいうように、「父母が婚姻関係になかった」という、子供が自ら選ぶことができず、かつ自ら修正する余地のないことを理由として、子に不利益を及ぼすことは許されるべきではありません。
婚外子の立場からすれば、「自分は、父母が婚姻関係になかったというだけで、婚姻関係にあった子(異父母の兄弟)の半分の権利しかない。」となれば、そこに「正義」はありません。
よって、私も最高裁の判断は妥当と考えています。
ただ、単純な話で終わってはいけない。
この問題は、相続制度に関することであって、相続制度は、その国の伝統、社会事情、国民感情、婚姻や親子関係への意識や規律を総合的に考慮して法律によって制度が確立されるべき問題であって、「どの国でも通用する絶対的正義」が存在するわけではありません。
つまり、どんな相続制度の法律にするかは、その国ごとに裁量の幅が認められるものだということです(立法裁量といいます)。
この婚外子の相続格差は、もともと明治31年制定の民法で、当時の「家制度」を維持するため、婚外子も戸主となれることから、2分の1の権利を認めて制定されたもの。
敗戦後の民法改正でも「法律婚の尊重と婚外子の保護の調整」を図るために存続されたものです。
「家制度」に起因すると、それだけでヒステリーに反応する向きもありますが、制定時も敗戦後も、我が国の国家状況、国民意識等からして、認められて当然の規定です。
ちなみに、「人権、人権、平等、平等」と声の大きい欧米諸国では、キリスト教の影響から、もともとは婚外子には法的権利が認められていなかったのです。それが、1960年代になってから国際的な人権尊重の潮流が起き、婚外子の権利除外規定が撤廃されていった歴史があります。
ですから、我が国でも、もともとは国民意識として法律婚を尊重するために規定していたものですが、時代も進展し、子を個人として尊重し権利を保障すべきという考えが確立されてきたことで、現在では、このような婚外子の相続分に格差を設けるのはよろしくないと判断するに至ったと考えるべきです。
「もともと日本は悪かった」的な言説は論外です。
そのうえで、これは相続制度の問題であり、相続に関わるのは、「子」だけではありません。
相続に関与する「配偶者」、「嫡出子」、「非嫡出子(婚外子)」には、いずれにもそれぞれの「正義」があり、その「正義」は相互に矛盾をはらんでいます。
今回の最高裁の判断を受けて、嫡出子の側は「幸せな家庭を壊された上に、家から追い出された」とコメントしています。
仮に相続財産として家屋しかなかった場合、(嫡出子と同等の権利が認められる)婚外子からの請求を受けると、配偶者が老後の居住場所を失う可能性もあるわけです。
配偶者には、結婚をして共同で財産を形成して老後に備えてきたという「正義」がある。法律婚を守ってきたという「正義」がある。
今回の最高裁判断を受けて、法改正がされます。
私は、その際に、配偶者を手厚く保護するための配慮がされるべきだと考えています。
最高裁判決を受けた報道に接したとき
「我が国伝統の家族意識への危機が…」
とか
「法の賢慮が悪しき平等主義に負けた…」
などと保守派と称する方々から大上段に構えた意見がありましたが、私は必ずしも賛成しません。
私たち国民の意識にある「家族を大切にする思い」、「法律婚の尊重」は、様々な立場の「正義」との配慮とともに大切にされるべきです。
法律では、相続にあたって配偶者への手厚い配慮を規定するなどで、様々に「正義」への配慮が考えられるべきです。
保守であればこそです。
10月からの国会審議でも、単純化しない保守の議論を展開したいと考えています。
Posted by miyazakimasahisa at 12:00│Comments(0)