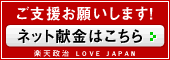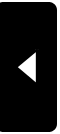2013年09月11日
婚外子の相続格差違憲判決と保守の思想
先日、最高裁判所から、婚外子(結婚していない男女間に産まれた子)の相続格差に関する民法900条4号但書の規定が憲法違反であるとの判断が下されました。
10月15日開会予定の臨時国会でこの法律の改正が審議されるものと思います。
この判決に対し、「保守」と称する方々から「法の賢慮が負けた」などと疑問の声が出たり、法改正に後ろ向きのコメントが出されているようです。
今回は、保守の立場から、この問題に触れてみます。
まず、憲法違反と言われた規定は、どんな定めなのか。
これは「嫡出でない子の相続分は嫡出である子の相続分の2分の1」とされた規定です。
結婚した男女から生まれた子のことを「嫡出子」といい、タイトルにある「婚外子」のことは「非嫡出子」といいます。
例えば、男が妻との間の子がいて、妻以外の女性との間にも子がいて、この男性が亡くなったという場合、妻以外の女性との子は、妻との間の子の半分の相続権しか認められないということです。いわゆる本妻の子が優先されているのです。
子供は親を選べません。
最高裁もいうように、「父母が婚姻関係になかった」という、子供が自ら選ぶことができず、かつ自ら修正する余地のないことを理由として、子に不利益を及ぼすことは許されるべきではありません。
婚外子の立場からすれば、「自分は、父母が婚姻関係になかったというだけで、婚姻関係にあった子(異父母の兄弟)の半分の権利しかない。」となれば、そこに「正義」はありません。
よって、私も最高裁の判断は妥当と考えています。
ただ、単純な話で終わってはいけない。
この問題は、相続制度に関することであって、相続制度は、その国の伝統、社会事情、国民感情、婚姻や親子関係への意識や規律を総合的に考慮して法律によって制度が確立されるべき問題であって、「どの国でも通用する絶対的正義」が存在するわけではありません。
つまり、どんな相続制度の法律にするかは、その国ごとに裁量の幅が認められるものだということです(立法裁量といいます)。
この婚外子の相続格差は、もともと明治31年制定の民法で、当時の「家制度」を維持するため、婚外子も戸主となれることから、2分の1の権利を認めて制定されたもの。
敗戦後の民法改正でも「法律婚の尊重と婚外子の保護の調整」を図るために存続されたものです。
「家制度」に起因すると、それだけでヒステリーに反応する向きもありますが、制定時も敗戦後も、我が国の国家状況、国民意識等からして、認められて当然の規定です。
ちなみに、「人権、人権、平等、平等」と声の大きい欧米諸国では、キリスト教の影響から、もともとは婚外子には法的権利が認められていなかったのです。それが、1960年代になってから国際的な人権尊重の潮流が起き、婚外子の権利除外規定が撤廃されていった歴史があります。
ですから、我が国でも、もともとは国民意識として法律婚を尊重するために規定していたものですが、時代も進展し、子を個人として尊重し権利を保障すべきという考えが確立されてきたことで、現在では、このような婚外子の相続分に格差を設けるのはよろしくないと判断するに至ったと考えるべきです。
「もともと日本は悪かった」的な言説は論外です。
そのうえで、これは相続制度の問題であり、相続に関わるのは、「子」だけではありません。
相続に関与する「配偶者」、「嫡出子」、「非嫡出子(婚外子)」には、いずれにもそれぞれの「正義」があり、その「正義」は相互に矛盾をはらんでいます。
今回の最高裁の判断を受けて、嫡出子の側は「幸せな家庭を壊された上に、家から追い出された」とコメントしています。
仮に相続財産として家屋しかなかった場合、(嫡出子と同等の権利が認められる)婚外子からの請求を受けると、配偶者が老後の居住場所を失う可能性もあるわけです。
配偶者には、結婚をして共同で財産を形成して老後に備えてきたという「正義」がある。法律婚を守ってきたという「正義」がある。
今回の最高裁判断を受けて、法改正がされます。
私は、その際に、配偶者を手厚く保護するための配慮がされるべきだと考えています。
最高裁判決を受けた報道に接したとき
「我が国伝統の家族意識への危機が…」
とか
「法の賢慮が悪しき平等主義に負けた…」
などと保守派と称する方々から大上段に構えた意見がありましたが、私は必ずしも賛成しません。
私たち国民の意識にある「家族を大切にする思い」、「法律婚の尊重」は、様々な立場の「正義」との配慮とともに大切にされるべきです。
法律では、相続にあたって配偶者への手厚い配慮を規定するなどで、様々に「正義」への配慮が考えられるべきです。
保守であればこそです。
10月からの国会審議でも、単純化しない保守の議論を展開したいと考えています。
10月15日開会予定の臨時国会でこの法律の改正が審議されるものと思います。
この判決に対し、「保守」と称する方々から「法の賢慮が負けた」などと疑問の声が出たり、法改正に後ろ向きのコメントが出されているようです。
今回は、保守の立場から、この問題に触れてみます。
まず、憲法違反と言われた規定は、どんな定めなのか。
これは「嫡出でない子の相続分は嫡出である子の相続分の2分の1」とされた規定です。
結婚した男女から生まれた子のことを「嫡出子」といい、タイトルにある「婚外子」のことは「非嫡出子」といいます。
例えば、男が妻との間の子がいて、妻以外の女性との間にも子がいて、この男性が亡くなったという場合、妻以外の女性との子は、妻との間の子の半分の相続権しか認められないということです。いわゆる本妻の子が優先されているのです。
子供は親を選べません。
最高裁もいうように、「父母が婚姻関係になかった」という、子供が自ら選ぶことができず、かつ自ら修正する余地のないことを理由として、子に不利益を及ぼすことは許されるべきではありません。
婚外子の立場からすれば、「自分は、父母が婚姻関係になかったというだけで、婚姻関係にあった子(異父母の兄弟)の半分の権利しかない。」となれば、そこに「正義」はありません。
よって、私も最高裁の判断は妥当と考えています。
ただ、単純な話で終わってはいけない。
この問題は、相続制度に関することであって、相続制度は、その国の伝統、社会事情、国民感情、婚姻や親子関係への意識や規律を総合的に考慮して法律によって制度が確立されるべき問題であって、「どの国でも通用する絶対的正義」が存在するわけではありません。
つまり、どんな相続制度の法律にするかは、その国ごとに裁量の幅が認められるものだということです(立法裁量といいます)。
この婚外子の相続格差は、もともと明治31年制定の民法で、当時の「家制度」を維持するため、婚外子も戸主となれることから、2分の1の権利を認めて制定されたもの。
敗戦後の民法改正でも「法律婚の尊重と婚外子の保護の調整」を図るために存続されたものです。
「家制度」に起因すると、それだけでヒステリーに反応する向きもありますが、制定時も敗戦後も、我が国の国家状況、国民意識等からして、認められて当然の規定です。
ちなみに、「人権、人権、平等、平等」と声の大きい欧米諸国では、キリスト教の影響から、もともとは婚外子には法的権利が認められていなかったのです。それが、1960年代になってから国際的な人権尊重の潮流が起き、婚外子の権利除外規定が撤廃されていった歴史があります。
ですから、我が国でも、もともとは国民意識として法律婚を尊重するために規定していたものですが、時代も進展し、子を個人として尊重し権利を保障すべきという考えが確立されてきたことで、現在では、このような婚外子の相続分に格差を設けるのはよろしくないと判断するに至ったと考えるべきです。
「もともと日本は悪かった」的な言説は論外です。
そのうえで、これは相続制度の問題であり、相続に関わるのは、「子」だけではありません。
相続に関与する「配偶者」、「嫡出子」、「非嫡出子(婚外子)」には、いずれにもそれぞれの「正義」があり、その「正義」は相互に矛盾をはらんでいます。
今回の最高裁の判断を受けて、嫡出子の側は「幸せな家庭を壊された上に、家から追い出された」とコメントしています。
仮に相続財産として家屋しかなかった場合、(嫡出子と同等の権利が認められる)婚外子からの請求を受けると、配偶者が老後の居住場所を失う可能性もあるわけです。
配偶者には、結婚をして共同で財産を形成して老後に備えてきたという「正義」がある。法律婚を守ってきたという「正義」がある。
今回の最高裁判断を受けて、法改正がされます。
私は、その際に、配偶者を手厚く保護するための配慮がされるべきだと考えています。
最高裁判決を受けた報道に接したとき
「我が国伝統の家族意識への危機が…」
とか
「法の賢慮が悪しき平等主義に負けた…」
などと保守派と称する方々から大上段に構えた意見がありましたが、私は必ずしも賛成しません。
私たち国民の意識にある「家族を大切にする思い」、「法律婚の尊重」は、様々な立場の「正義」との配慮とともに大切にされるべきです。
法律では、相続にあたって配偶者への手厚い配慮を規定するなどで、様々に「正義」への配慮が考えられるべきです。
保守であればこそです。
10月からの国会審議でも、単純化しない保守の議論を展開したいと考えています。
Posted by miyazakimasahisa at
12:00
│Comments(0)
2013年06月22日
憲法96条の改正
Facebookに書いたところ反響があった憲法改正の問題。
以前にこのブログで少し書きましたが、今回は96条のことを書いてみます。
私は、憲法96条の改正が必要であると考えています。
その理由は、憲法を我々国民にとって身近なものとして取り返す必要があるからです。
いま、憲法が私たちの生活に身近なものとなっていません。
その理由のひとつは、憲法が改正される可能性が、現実的にはないからです。
現在の憲法は、改正の発議のためには衆議院、参議院、それぞれで「総議員の3分の2の同意」が必要とされています。
その上で国民投票にふされます。
いかなる内容であっても、憲法を改正すべきか否かにつき、主権者である国民の意思を問うには、衆参両院で、いずれも3分の2以上の同意を取らないといけないわけで、政治の現実からすれば、ほぼ不可能といえるハードルとなります。
憲法改正に現実感がないのは、このせいです。
国民の側からすると発議されることはほぼないのですから、国民投票に参加することもない。
つまり、「憲法改正の是非を問われる機会はない」と思うのが普通の感覚です。
これが結果として、私たちと憲法との間にとても届かない距離を生じさせ、憲法が身近な存在ではなくなっていると思っています。
憲法改正がありうる状態となれば、改正を是とする人も、そうではない人も、憲法の意味、改正の是非を検討することとなります。
この国の歴史、現状、周辺の環境など様々なことを検討しなければなりません。
そうなることで、あらためて憲法が私たちの生活に身近な存在となる。
一人ひとりの国民が考える機会をもつことで、結果として憲法が身近な存在になる、私はそう考えています。
よく憲法は最高法規だから、法律と同様に「過半数」で決められるべきではないという意見がありますが、これは誤りです。
まず、法律は過半数の決議で成立しますが、その前提となる定足数は3分の1です。
ですから、最少では衆参両院で6分の1を超える議員の賛成で法律を成立させることができます。
これに対して、憲法改正の発議は「総議員」に対するものですから、「過半数」とした場合でも、衆参両院で2分の1を越える議員の賛成がなければ発議できません。
さらに、憲法改正の場合、国会の手続きは「発議」だけですから、その後国民投票に付されます。
これに対して、法律の制定に国民投票は存在しません。
憲法96条を改正して発議要件を「過半数」とした場合であっても、法律を制定する際の要件とはまったく異なり、法律と同様にするものではないのです。
憲法は、この国の根本法。
だからこそ、国民一人ひとりが誇りをもてる内容で、身近な存在としてあるべきです。
それゆえ、改正が現実的にありうる状態に置くべきで、そのためには「過半数」への改正が必要と考えています。
なお、この憲法96条を「過半数」と改正するためであって、衆参両院で総議員の3分の2以上の同意で発議を可決し、国民投票に付して過半数の同意が必要であることはもちろんです。
憲法96条について考えていることを記してみました。
最後までお読み下さったことを感謝申し上げます。
以前にこのブログで少し書きましたが、今回は96条のことを書いてみます。
私は、憲法96条の改正が必要であると考えています。
その理由は、憲法を我々国民にとって身近なものとして取り返す必要があるからです。
いま、憲法が私たちの生活に身近なものとなっていません。
その理由のひとつは、憲法が改正される可能性が、現実的にはないからです。
現在の憲法は、改正の発議のためには衆議院、参議院、それぞれで「総議員の3分の2の同意」が必要とされています。
その上で国民投票にふされます。
いかなる内容であっても、憲法を改正すべきか否かにつき、主権者である国民の意思を問うには、衆参両院で、いずれも3分の2以上の同意を取らないといけないわけで、政治の現実からすれば、ほぼ不可能といえるハードルとなります。
憲法改正に現実感がないのは、このせいです。
国民の側からすると発議されることはほぼないのですから、国民投票に参加することもない。
つまり、「憲法改正の是非を問われる機会はない」と思うのが普通の感覚です。
これが結果として、私たちと憲法との間にとても届かない距離を生じさせ、憲法が身近な存在ではなくなっていると思っています。
憲法改正がありうる状態となれば、改正を是とする人も、そうではない人も、憲法の意味、改正の是非を検討することとなります。
この国の歴史、現状、周辺の環境など様々なことを検討しなければなりません。
そうなることで、あらためて憲法が私たちの生活に身近な存在となる。
一人ひとりの国民が考える機会をもつことで、結果として憲法が身近な存在になる、私はそう考えています。
よく憲法は最高法規だから、法律と同様に「過半数」で決められるべきではないという意見がありますが、これは誤りです。
まず、法律は過半数の決議で成立しますが、その前提となる定足数は3分の1です。
ですから、最少では衆参両院で6分の1を超える議員の賛成で法律を成立させることができます。
これに対して、憲法改正の発議は「総議員」に対するものですから、「過半数」とした場合でも、衆参両院で2分の1を越える議員の賛成がなければ発議できません。
さらに、憲法改正の場合、国会の手続きは「発議」だけですから、その後国民投票に付されます。
これに対して、法律の制定に国民投票は存在しません。
憲法96条を改正して発議要件を「過半数」とした場合であっても、法律を制定する際の要件とはまったく異なり、法律と同様にするものではないのです。
憲法は、この国の根本法。
だからこそ、国民一人ひとりが誇りをもてる内容で、身近な存在としてあるべきです。
それゆえ、改正が現実的にありうる状態に置くべきで、そのためには「過半数」への改正が必要と考えています。
なお、この憲法96条を「過半数」と改正するためであって、衆参両院で総議員の3分の2以上の同意で発議を可決し、国民投票に付して過半数の同意が必要であることはもちろんです。
憲法96条について考えていることを記してみました。
最後までお読み下さったことを感謝申し上げます。
Posted by miyazakimasahisa at
13:28
│Comments(3)
2013年06月11日
生きること
生きることの尊さを学ばせてもらった。
自らが障害をもっていることをものともせず、障害がある人を支援するためのNPO法人を立ち上げたスゴイ人がいる。
我如古盛健さんと宮城幸春さん。
宮城さんは、19歳の時に海で事故にあい頚椎損傷で首から下が動かなくなった。元気で海遊びに行って事故にあい境遇が一遍。どん底に落ち込んだことは想像に難くない。
我那覇さんは進行性の病気に罹患し、少しずつ身体が自由に動かなくなっている。そんな彼が車イスから驚くような三線演奏をして子供たちが踊り出す。感動の連鎖をつくっている。
宮城さんが言う「指が一本でも動けば、健常者と同じ仕事ができるのに」
宮城さんは首から下はまったく動かない。それでも口にくわえたペンでパソコンを操り、今では電光掲示板広告のデザインまでこなす。
感動した。
というよりも、心を洗われた思い。
生きているこの瞬間を大切に、生を閉じるその時まで精一杯生きる。
私も誓ってます。
「父ちゃんは一生懸命生きたぜ」
死を前にしたとき、子供たちに笑ってそう言い残す生き様でありたい。
力強い仲間ができた。
彼らと一緒に笑顔で精進したいと思っています。
自らが障害をもっていることをものともせず、障害がある人を支援するためのNPO法人を立ち上げたスゴイ人がいる。
我如古盛健さんと宮城幸春さん。
宮城さんは、19歳の時に海で事故にあい頚椎損傷で首から下が動かなくなった。元気で海遊びに行って事故にあい境遇が一遍。どん底に落ち込んだことは想像に難くない。
我那覇さんは進行性の病気に罹患し、少しずつ身体が自由に動かなくなっている。そんな彼が車イスから驚くような三線演奏をして子供たちが踊り出す。感動の連鎖をつくっている。
宮城さんが言う「指が一本でも動けば、健常者と同じ仕事ができるのに」
宮城さんは首から下はまったく動かない。それでも口にくわえたペンでパソコンを操り、今では電光掲示板広告のデザインまでこなす。
感動した。
というよりも、心を洗われた思い。
生きているこの瞬間を大切に、生を閉じるその時まで精一杯生きる。
私も誓ってます。
「父ちゃんは一生懸命生きたぜ」
死を前にしたとき、子供たちに笑ってそう言い残す生き様でありたい。
力強い仲間ができた。
彼らと一緒に笑顔で精進したいと思っています。
Posted by miyazakimasahisa at
13:28
│Comments(2)
2013年06月03日
北方領土視察で感じたもの
自由民主党の領土に関する特命委員会で、2日間にわたり北方領土を視察した。
根室市の納沙布岬から知床自然遺産の羅臼町まで。
視察とともに2日間にわたり様々な方々と意見交換をした。
元島民の方から、あらためて当時体験した厳しい歴史を聞かせていただいた。
元島民の平均年齢は79歳になった。「元気なうちに墓参りをしたい」という声は胸に刺さった。
漁業の現実は深刻だ。豊かな海の根室海峡ではjロシアのトロール船が操業を繰り返す。平成元年には10万トンを超えていたスケトウダラの漁獲高は、今では1万トン程度。彼らには資源管理の考えが通じない。
夜の街に出てみたらスナックは繁盛していて、なんかうれしかった。JRが廃線となった道東の地で商工会を盛り上げようとする仲間も頑張っている。
老いも若きも一生懸命生活している。
歴史の体験や学んだ歴史に縛られず、前を向いて歩いている。
合理的に主張するべきは主張して、でも自分の足元をしっかりと見つめている。
いつも「その先」を見つめ、行動する姿勢だ。
もとより領土の問題は地域の問題ではない。
国家が解決すべき課題。
だから、私たち一人ひとりの国民が我が事として関わる必要がある。
政治を動かす国民の関心と意見が不可欠だ。
納沙布岬からわずか3.7㎞の貝殻島も、羅臼から望む大きな国後島も、あいにくの天候で霧にかすんで見えなかった。
けれど、この「霧」を晴らすことが政治の役目だと実感した。
雪が残り、桜が満開の羅臼町から、梅雨の合間で海水浴も楽しめる沖縄に戻った。
その気温差約20度。
この国は縦に長いね。
続きを読む
根室市の納沙布岬から知床自然遺産の羅臼町まで。
視察とともに2日間にわたり様々な方々と意見交換をした。
元島民の方から、あらためて当時体験した厳しい歴史を聞かせていただいた。
元島民の平均年齢は79歳になった。「元気なうちに墓参りをしたい」という声は胸に刺さった。
漁業の現実は深刻だ。豊かな海の根室海峡ではjロシアのトロール船が操業を繰り返す。平成元年には10万トンを超えていたスケトウダラの漁獲高は、今では1万トン程度。彼らには資源管理の考えが通じない。
夜の街に出てみたらスナックは繁盛していて、なんかうれしかった。JRが廃線となった道東の地で商工会を盛り上げようとする仲間も頑張っている。
老いも若きも一生懸命生活している。
歴史の体験や学んだ歴史に縛られず、前を向いて歩いている。
合理的に主張するべきは主張して、でも自分の足元をしっかりと見つめている。
いつも「その先」を見つめ、行動する姿勢だ。
もとより領土の問題は地域の問題ではない。
国家が解決すべき課題。
だから、私たち一人ひとりの国民が我が事として関わる必要がある。
政治を動かす国民の関心と意見が不可欠だ。
納沙布岬からわずか3.7㎞の貝殻島も、羅臼から望む大きな国後島も、あいにくの天候で霧にかすんで見えなかった。
けれど、この「霧」を晴らすことが政治の役目だと実感した。
雪が残り、桜が満開の羅臼町から、梅雨の合間で海水浴も楽しめる沖縄に戻った。
その気温差約20度。
この国は縦に長いね。
続きを読む
Posted by miyazakimasahisa at
18:00
│Comments(1)
2013年05月24日
認可外保育施設への防音工事
沖縄には待機児童が多い。
都道府県別では、東京都についで全国で2番目。
子供を預ける保育所についても認可外が多い。
全国では認可保育施設が中心ですが、沖縄では認可外施設が多いのです。
数字をあげると
全国では施設数で認可2万3千箇所に対し認可外7千箇所。
定員では認可224万人に対し認可外18万人。
これに対して、沖縄では施設数で認可393箇所に対し認可外448箇所と逆転状態。
定員では認可3万3千人に対し認可外2万2千人。
米軍基地の周辺にも保育所があります。
日々、爆音にさらされている。
ところが、防音工事の助成対象は、認可保育所だけ。
認可外保育施設には防音工事の助成がされていないのです。
調べてみました。
防音工事の助成を定めるのは「防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律」です。
学校や病院等と並んで保育所も対象となっているのですが、同法を受けた施行令で「保育所」は児童福祉法で県知事の認可を受けたものとされているからです。
しかし、預けられている子供にとっては、そこが認可保育所であるか認可外であるかは関係ない。
子供を預けている親にしても、沖縄に認可保育施設が少ない実情からすれば、認可に預けたいけど入れないので認可外に預けているという方もいる。防音工事の助成対象が認可に限定されているとして納得できるものではない。
弁護士として人権擁護につとめてきた身です。
だから、私は、認可外保育施設に対する防音工事の助成を進めたいと考えています。
この問題、実はこれまで沖縄から声をあげていなかったことです。
気が付かないのか、出来そうもないと思われていたからか。
そこで、私は、平成25年4月15日の衆議院予算委員会で質問しました。
そして、小野寺防衛大臣から、積極的に取り組むことへの答弁を引き出しました。
実は、これ以降、防衛省と認可外保育施設に対する防音工事助成の実施に向けて、具体的な協議を進めています。
出来るだけ早く、具体的な実施計画等をご報告できるようにします。
こうやって問題提起すると、新聞報道が出たり、同じことを質問に取り上げる野党の国会議員さんが出てきたり、要請活動に邁進する市長さんが出てきます。
私は、認可外保育施設への防音工事の助成を進める第一人者として、その実現に力を尽くします。
政権与党の立場にあるから迅速に出来ることがあります。
反対の声を上げるだけじゃダメ。
前を向いて、若い力で未来を切り拓いていく。
だから、
具体的な仕事をして成果をあげるのが、私の政治家としてのスタイルです。
この問題も、そのひとつです。
沖縄のため、日本のため、これからも仕事をして、しっかりと成果をあげていきます。

都道府県別では、東京都についで全国で2番目。
子供を預ける保育所についても認可外が多い。
全国では認可保育施設が中心ですが、沖縄では認可外施設が多いのです。
数字をあげると
全国では施設数で認可2万3千箇所に対し認可外7千箇所。
定員では認可224万人に対し認可外18万人。
これに対して、沖縄では施設数で認可393箇所に対し認可外448箇所と逆転状態。
定員では認可3万3千人に対し認可外2万2千人。
米軍基地の周辺にも保育所があります。
日々、爆音にさらされている。
ところが、防音工事の助成対象は、認可保育所だけ。
認可外保育施設には防音工事の助成がされていないのです。
調べてみました。
防音工事の助成を定めるのは「防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律」です。
学校や病院等と並んで保育所も対象となっているのですが、同法を受けた施行令で「保育所」は児童福祉法で県知事の認可を受けたものとされているからです。
しかし、預けられている子供にとっては、そこが認可保育所であるか認可外であるかは関係ない。
子供を預けている親にしても、沖縄に認可保育施設が少ない実情からすれば、認可に預けたいけど入れないので認可外に預けているという方もいる。防音工事の助成対象が認可に限定されているとして納得できるものではない。
弁護士として人権擁護につとめてきた身です。
だから、私は、認可外保育施設に対する防音工事の助成を進めたいと考えています。
この問題、実はこれまで沖縄から声をあげていなかったことです。
気が付かないのか、出来そうもないと思われていたからか。
そこで、私は、平成25年4月15日の衆議院予算委員会で質問しました。
そして、小野寺防衛大臣から、積極的に取り組むことへの答弁を引き出しました。
実は、これ以降、防衛省と認可外保育施設に対する防音工事助成の実施に向けて、具体的な協議を進めています。
出来るだけ早く、具体的な実施計画等をご報告できるようにします。
こうやって問題提起すると、新聞報道が出たり、同じことを質問に取り上げる野党の国会議員さんが出てきたり、要請活動に邁進する市長さんが出てきます。
私は、認可外保育施設への防音工事の助成を進める第一人者として、その実現に力を尽くします。
政権与党の立場にあるから迅速に出来ることがあります。
反対の声を上げるだけじゃダメ。
前を向いて、若い力で未来を切り拓いていく。
だから、
具体的な仕事をして成果をあげるのが、私の政治家としてのスタイルです。
この問題も、そのひとつです。
沖縄のため、日本のため、これからも仕事をして、しっかりと成果をあげていきます。

Posted by miyazakimasahisa at
12:50
│Comments(1)
2013年05月04日
憲法改正が必要だ

憲法記念日にあたり、メディアから取材を受け報道されます。
「憲法の改正」をどう思いますか?
私は、日本国憲法を改正する必要があると考えています。
改正を必要とする理由は、9条に象徴されるように現憲法には時代の進展に合わない不備があるからですが、もうひとつ、沖縄県民の立場から改正の必要を指摘をしています。
現憲法の制定に沖縄県民は関与していません。
現憲法は、昭和21年第90回帝国議会において、大日本帝国憲法を改正するという手続きで成立しました。
この第90回帝国議会はもちろん、これに先立ち憲法草案を審議した第88回、第89回の帝国議会にも沖縄県民の代表は参加していません。
戦後米軍統治下にあった沖縄県の代表が国会に代表を送ることは、本土復帰を目前にした昭和45年まで待たねばなりませんでした。
憲法は国家の根本法であることからしても、その制定過程にはすべての国民もしくは国民代表が参加することが必要です。
すべての国民が参加することによって、憲法が正当性の契機をもつといえます。
だから、私は、我が国の憲法は、沖縄県民も参加して、新たに全国民の手で制定されることが必要であると考えています。
簡単にいえば、沖縄県民は憲法の制定に関与することもできなかったのだから、これに従えというのもおかしな話で、沖縄県民も参加してきちんと国の根本の決まりを創ろうという認識です。
それゆえ、憲法は全面的に改定し、新しい憲法を制定すべきと考えています。
もちろん、国民の間で必要性に共通の理解を得ているものは、それを採用するべきと考えますから、国民主権、基本的人権の尊重、平和主義の三大原則は堅持されなければなりません。
そのうえで、憲法改正について最大の焦点は9条です。
私は、平和主義、戦争放棄については維持しつつ、9条2項について改正する必要があるという意見です。
安全保障は国家が果たすべきもっとも重要な責務のひとつですから、自衛隊の存在と役割を憲法に明記し、憲法で規律する必要があります。自衛隊が違憲であるというような時代錯誤な見解が生じうる現憲法の規定は、第2次大戦直後の国際情勢の遺物です。
平和は尊く、戦争は絶対に避けなければいけないことに異論はないでしょう。
歴史が証明するように、平和はただ念じることでは維持できず、今を生きる者の不断の努力によって維持され勝ち取るものです。
「9条に手を付けることは戦争への途を開くものだ」とか「戦争ができる国になる」などという感情に支配された議論から、私たちの世代は卒業したいと考えています。
人は感情に生きる動物ですから感情を否定するものではありませんが、国の在り方を議論するときには、感情に流されることなく、理性的に建設的に、現実感をもって考えたいものです。 続きを読む
Posted by miyazakimasahisa at
23:49
│Comments(1)
2013年04月29日
沖縄でモーターレースを

こんばんは、宮﨑政久です。
自民党モータースポーツ振興議員連盟で富士スピードウェイを視察し、SUPER GTレースを観戦しました。
実は、沖縄県豊見城市で公道を利用したSUPER GTレースの開催を準備しています。
これを目指して、SUPER GTには沖縄チームも参戦しています(今回は4位でした)。
F1のモナコグランプリのように、沖縄の青い海を背景にしたビーチサイドの公道でモーターレース。
素晴らしいと思いませんか。
夢があるでしょ。
国内外から多くの人を沖縄に呼び込める起爆剤になると思います。
沖縄がただ振興策に頼るのではなく、自らの工夫の中で成長し、多くの人を呼び込む事業を創り上げようと努力しています。
もう少しで実現しそうなところまで来ました
私は、この主体性が好きで、お手伝いしています。
そのために、公道でのモータースポーツ振興を図る議員立法の準備も進めています。
モータースポーツを我が国でもカルチャーとして定着させていくために。
沖縄に新しい成長のエンジンをつくるために。
沖縄が先頭にたって日本の繁栄を導いていく。
モータースポーツの世界で実践したいと思っています。
PS 自民党議連の視察では、古屋圭司国家公安委員長、三原じゅん子参議院議員に大変にお世話になりました。
ありがとうございました。
レーサーだった三原じゅん子先生は大人気でした。
近藤真彦さんもオーラありましたよ。 続きを読む
Posted by miyazakimasahisa at
23:50
│Comments(2)
2013年04月28日
主権回復記念式典に参加して

こんにちは、宮﨑政久です。
「主権回復・国際社会復帰を記念する式典」に参加しました。
沖縄県民として、国会議員として、この式典に参加して良かったと思いました。
サンフランシスコ講和条約が発効して、我が国は被占領国の立場を脱しました。
他方、沖縄は奄美、小笠原とともに本土から切り離され、特に沖縄は昭和47年の復帰に至るまで苦難の歴史をたどりました。
そして、講和条約と同時に締結・発効した日米安保条約のもと、沖縄には米軍基地が増え、それが今もって続く沖縄の過重な基地負担の原因となり、今も市民生活へ影響しています。
だから、この式典に様々な意見があることはわかります。
現に、私も先輩方からあの当時の苦しかった話を聞かせて頂くたびに、複雑な思いを胸に抱えていました。
しかし、私は、今回の式典は、日本人がひとつになって未来を切り拓く機会になったと思います。
沖縄の県民は、DNAでも南方縄文人の系譜にあり、「おもろそうし」に万葉ことばがあるように、人類学的にも文化的にもまぎれもなく日本人です。
私は、日本人がひとつになって、困難な課題を解決し、豊かな国にしたいと思っています。
そのためには、沖縄の苦難の歴史と今も続く過重な負担の事実に対して、すべての国民が思いを寄せてほしいと思っています。
そうしないと、日本の国として、基地負担を筆頭として今も続く沖縄の過重な負担を軽減することは難しいし、
この式典が目指す、「我が国が目指すべき将来像をともに考える契機」とすることも出来ないから。
安倍総理大臣は式辞の中で
「特に若い世代の人たちに、沖縄が経てきた辛苦に深く思いを寄せる努力をすべきだと呼び掛ける」
と述べられました。
良かった。
私も、自民党全議員懇談会でこの式典に対する沖縄の思いを発言し、菅官房長官にも首相官邸に赴いて直接要請するなどして、今日の式典を迎えました。
それは、この式典を契機として、国民が、沖縄の歴史と現実にも思いをはせ、一致して未来を切り拓く機会にしてほしいという思いからでした。
歴史を学び、歴史に縛られるのではなく、明日へ生かしていく。
沖縄の過重な基地負担を解消し、もっと豊かな沖縄をつくりたい。
そのためには、ただ反対の声を上げるだけはダメだ、具体的に政治に参画していくんだ。
それこそが、真に沖縄のため、日本のためになる。
だから、私は、自分の全存在をかけて、「かけはし」になるんだ。
安倍総理の言葉を聞き、政治を志した時の思いと
先輩方から聞いた苦しかった時の話が胸にこみあげ
式典中、涙しました。
この思いを胸に、沖縄のため、日本のため、全力で走ります。
続きを読む
タグ :主権回復の日 沖縄 日本
Posted by miyazakimasahisa at
13:40
│Comments(3)
2013年04月18日
拘置所の中で

こんばんは、宮﨑政久です。
今日は、更生保護を考える議連で東京拘置所を視察しました。
建物は12階建で要塞のような堅牢さ
CTを備えた医療施設もある。
職員数792名、収容定員3010名
多数の職員の方々の手でしっかりとした運用がされていることに感心しました。
今日は、施設内部で、未決の方・受刑者の実際の生活も直接見ました。
ちょうど夕食の時間でした。
ここにもひとつの世界がある。
収容されている方の数だけの人生がある。
食事をしている中、この場に収容されていることへの思いは様々でしょう。
弁護士として刑事弁護をしている時と同じ思いにかられた。
被疑者、被告人の立場に立って事件を分析し、彼らの人生を見つめていたあの時と同じ感覚。
この人はどうしてここにいるのか
事件をどう受け止めているのか
家族はいるのか
誰か面会に来てくれているのか
施設と運用状況の視察なのに、人への思いが先にたっていた2時間でした。
続きを読む
タグ :拘置所 更生保護 刑事 面会
Posted by miyazakimasahisa at
18:46
│Comments(0)
2013年04月13日
ハーグ条約

こんばんは、宮﨑政久です。
今日は、衆議院法務委員会でハーグ条約関連の質問に立ちました。
私の最大の関心事は裁判管轄の問題。
法案で東京と大阪にしか裁判管轄を認めていないことから、沖縄県民が不利益にならないようにしたいということです。
沖縄では国際結婚が多い。これは沖縄に米軍基地が多いことを背景としています。
在日米軍人等10万3千人のうち、実に5万人の方がが沖縄で居住しています。
沖縄県では女性が日本人である国際結婚の比率が全国一番で、その中でも8割以上が米国人男性と沖縄の女性との国際結婚なんです。
出会いがあり、ハッピーな国際結婚が成立する。
しかし、日本人同士でも夫婦関係がうまくいかないことがあるように、国際結婚カップルでもうまくいかないことは起きる。
国際結婚をして外国で生活していた沖縄の女性が、夫婦関係が円満にいかず子供を連れて沖縄に戻ってきたところ、ハーグ条約に基づき、夫から子の引き渡しを求める裁判が起こされたというときに、日本でどのような裁判が行われるかを定めた手続法が、今回の法務委員会での審議対象です。
法案では、我が国の裁判は、東京家裁と大阪家裁で行われることとなっています。
私は、一貫して那覇家裁でも裁判管轄を認めるべきと主張しています。
ただ、今回の法案ではこれを実現することはできませんでした。
そうであれば、実際の運用で、沖縄県民に限らず遠隔地にいる日本国民が不利益を受けず、裁判を受ける権利を十分に保障してほしい、その一念で法務省、最高裁と協議を続けました。
具体的には、裁判管轄が認められないとしても、遠隔地の当事者が直接に裁判官に実情を訴える機会を保障してほしいということです。
当事者(つまり外国から子供を連れて逃げ帰ってきた人)が沖縄から大阪まで出向くとなれば、その費用負担は大きい。
そこで、裁判官が沖縄に出向いて当事者から直接に話を聞いてほしいのです。
テレビ会議を利用するだけでなく、裁判官が出張尋問の形式をとる運用を通常の形式にしてほしいということです。
そして、その費用(裁判官と書記官が出張する交通費、宿泊費)についても、当事者の負担とせず公費でまかなってもらう必要があります。
だって、費用が当事者負担であれば金銭的に余裕のある方しか活用できませんから。
こういった点について法務省、最高裁と協議を重ねました。
その結果、今日の質疑で、遠隔地の当事者への配慮として、裁判官が当事者の地元(那覇家裁)に出張することで当事者から直接話を聞くこと、その際の出張費用は公費でまかない当事者の負担としないこと、このような取扱いとすることに最高裁として今後周知徹底を図ること、となりました。
谷垣法務大臣からも、上記諸点をしっかりと実行する旨の力強い答弁をいただいたところです。
沖縄に国際結婚が多いのは、米軍基地が多いことに起因しているわけです。
それゆえ、安全保障や基地問題という側面でなく、県民の生活にかかわる面から、沖縄の過重な基地負担を具体的に軽減できたと思います。
省庁と協議を重ね、国会での質疑を通じて、県民の利益になる取組みができたことに、少しホッとしています。
この案件は、沖縄弁護士会からも強く要請されていました。
自分を育ててくれた弁護士会の要請に応えることができたことは、実はとてもうれしくて、内心安堵することでもありました。
続きを読む
タグ :ハーグ条約 国会 国際結婚
Posted by miyazakimasahisa at
01:00
│Comments(3)
2013年04月03日
春の嵐

こんにちは、宮﨑政久です。
今朝の東京は春の嵐。
強い風と雨で、両手で傘を支えながら20分歩いて議員会館へ。
結構濡れました。
今日の午前中は、衆議院経済産業委員会で省エネ法を採決。
先週質問に立った法案ですから思い入れをもって採決しました。
実は我が国の省エネ基準、特に断熱に関する基準は低くて、住宅等では熱損失が大きいものが多いのです。
これは、沖縄に限らず我が国では、地域に差があるといえ、夏の暑さをしのぐために家をつくってきた。
それゆえ風通し良くすることに配慮されていて、結果として断熱には配慮されておらず、冷房しても暖房しても、冷気や暖気が部屋から外に逃げてしまう構造になっているからだと思います。
断熱を進めることは省エネルギーにとても価値が高い。
実は、高断熱住宅では、ぜんそく、アトピー、アレルギーなどの改善率が高いという研究結果も出ています。
こんなことをもっと知ってもらえるようにしないと、高断熱住宅の普及は進まないと思ってます。
この国の将来のために、やるべきことはたくさんあるわけです。
午後も頑張りましょう!
続きを読む
Posted by miyazakimasahisa at
12:15
│Comments(2)
2013年04月01日
区切りの日

4月1日、新年度スタート。
しばらくご無沙汰をしていたこのブログも再出発します。
私のもとでは、後援会事務所で新しいスタッフが加入しました。
もうひとつ、法律事務所でも新人事務局スタッフが加入しました。
どちらも人数の少ない小さな事務所です。
テレビで見るような盛大な入社式をしてあげることはできませんが、新しい仲間を歓迎する気持ちはどの組織にも負けません。
そんな気持ちで新しい仲間を迎えた4月1日でした。
環境があらたになった人も、引き続きのポジションで頑張る方も、「今日から新年度。頑張るか。」と、心に「区切り」をつけることができる日。
「区切り」をつけることで、きっといいことがあるはず。
そういえば、18ホールで競技するゴルフも、3ホールごとに区切りをつけて、うまくいってもミスがあっても心機一転プレーを心がけるといいと、昔、恩師から教わったな。
経営の場面でも3か月を一区切りに四半期で経営を見つめるしね。
では、区切りをつけて頑張っていきましょう!
続きを読む
Posted by miyazakimasahisa at
23:55
│Comments(0)
2012年11月29日
読谷支部開き
本日は、読谷支部開きがありました。
天気の悪い中、
多くの皆様にお集まりいただきました。
本当にありがとうございました。
みやざきの想いを皆さんに共有いただきました。
皆さんからいただきましたあたたかい気持ち、
ご期待にお応えできるよう、
精一杯走ります。


天気の悪い中、
多くの皆様にお集まりいただきました。
本当にありがとうございました。
みやざきの想いを皆さんに共有いただきました。
皆さんからいただきましたあたたかい気持ち、
ご期待にお応えできるよう、
精一杯走ります。
Posted by miyazakimasahisa at
23:28
│Comments(1)
2012年11月29日
公開討論会
皆さんこんばんは。
秘書の大澤です。
昨日は、
日本青年会議所(JC)沖縄ブロック協議会主催によります
公開討論会がありました。
日曜日の沖縄タイムス、琉球新報の紙面座談会と同様
激しい論戦が繰り広げられました。

理想だけで政治はできない。
リアルな現実をみつめること。
情緒的に訴えるだけでなく、耳触りのいいことをいうだけでなく、具体的な政策を提示し、現実と格闘しながら一つずつ推進していくことが今こそ必要です。
私は共働きの子育て弁護士。
人に優しい社会の実現を目指して、小児デイケアへの公費助成拡充を訴えています。女性はもちろん子育てしながら働く者誰にも(子育ては母だけでするものではない)、そして子供に社会の手を差し伸べて、社会全体で子供たちを育てていきます。
基地、安全保障政策や憲法論だけが政治ではありません。
ひとりひとりの日々の生活を忘れずに走ります。
http://www.youtube.com/watch?v=YaxWBur0VCc
秘書の大澤です。
昨日は、
日本青年会議所(JC)沖縄ブロック協議会主催によります
公開討論会がありました。
日曜日の沖縄タイムス、琉球新報の紙面座談会と同様
激しい論戦が繰り広げられました。
理想だけで政治はできない。
リアルな現実をみつめること。
情緒的に訴えるだけでなく、耳触りのいいことをいうだけでなく、具体的な政策を提示し、現実と格闘しながら一つずつ推進していくことが今こそ必要です。
私は共働きの子育て弁護士。
人に優しい社会の実現を目指して、小児デイケアへの公費助成拡充を訴えています。女性はもちろん子育てしながら働く者誰にも(子育ては母だけでするものではない)、そして子供に社会の手を差し伸べて、社会全体で子供たちを育てていきます。
基地、安全保障政策や憲法論だけが政治ではありません。
ひとりひとりの日々の生活を忘れずに走ります。
http://www.youtube.com/watch?v=YaxWBur0VCc
2012年11月28日
西原支部事務所開き
本日は、
西原支部事務所開きが行われました。
大変多くの皆様にお集まりいただき、
ミヤザキを激励してくださいました。
本当にありがとうございました。

たくさんの皆様から激励の言葉を頂きました。
本当にありがとうございました。
みなさんの
ご期待に応えられるよう精一杯がんばります。





西原支部事務所開きが行われました。
大変多くの皆様にお集まりいただき、
ミヤザキを激励してくださいました。
本当にありがとうございました。
たくさんの皆様から激励の言葉を頂きました。
本当にありがとうございました。
みなさんの
ご期待に応えられるよう精一杯がんばります。





2012年11月15日
衆院選
おはようございます。
いよいよ衆院選がきます。
大きく動く。
必ず変革が来ます。
だから、新しい沖縄づくりをしたい。
この国を自信を持って前へ進めたい。
だから、チェンジ!
皆さんの力を貸して下さい。
今日も頑張りましょう!
いよいよ衆院選がきます。
大きく動く。
必ず変革が来ます。
だから、新しい沖縄づくりをしたい。
この国を自信を持って前へ進めたい。
だから、チェンジ!
皆さんの力を貸して下さい。
今日も頑張りましょう!
Posted by miyazakimasahisa at
10:24
│Comments(1)
2012年11月13日
会社訪問
本日は、
会社訪問をさせていただきました。
その中で、
赤字国債発行法案について、お話しさせていただきました。
皆さん熱心に話を聞いておられました。
質問も飛び交い、皆さんと意見交換させていただきました。

ありがとうございました!!
会社訪問をさせていただきました。
その中で、
赤字国債発行法案について、お話しさせていただきました。
皆さん熱心に話を聞いておられました。
質問も飛び交い、皆さんと意見交換させていただきました。
ありがとうございました!!
2012年11月12日
第98回秋の全島闘牛大会
皆さんこんにちは!!
秘書の大澤です。
昨日は、
秋の全島闘牛大会へ参加してまいりました。
話には聞いておりましたが、驚くほど多くの闘牛ファンの皆さんが
会場いっぱいにあふれておりました!!!
熱気あふれる会場内で、
仲井眞知事や参議院議員
島尻あいこ先生、その他多くの関係者の皆様のご挨拶がありました。
みやざきも紹介して頂きました。
ありがとうございます。



秘書の大澤です。
昨日は、
秋の全島闘牛大会へ参加してまいりました。
話には聞いておりましたが、驚くほど多くの闘牛ファンの皆さんが
会場いっぱいにあふれておりました!!!
熱気あふれる会場内で、
仲井眞知事や参議院議員
島尻あいこ先生、その他多くの関係者の皆様のご挨拶がありました。
みやざきも紹介して頂きました。
ありがとうございます。

Posted by miyazakimasahisa at
15:45
│Comments(2)
2012年11月10日
浦添市議 うらさき猛先生事務所開き
本日は、
浦添市議 うらさき猛先生の事務所開きでした。
会場は多くの方々で大変にぎわっておりました。
みやざきも
激励の挨拶をさせて頂きました。
浦添市議奥本先生からは、
力強い圧巻の挨拶が。
うらさき先生からは
誠実な人柄あふれる、決意の挨拶がありました。
うらさき先生ともどもに
みやざき政久もがんばってまいります!!


これからもどうぞよろしくお願い致します。
浦添市議 うらさき猛先生の事務所開きでした。
会場は多くの方々で大変にぎわっておりました。
みやざきも
激励の挨拶をさせて頂きました。
浦添市議奥本先生からは、
力強い圧巻の挨拶が。
うらさき先生からは
誠実な人柄あふれる、決意の挨拶がありました。
うらさき先生ともどもに
みやざき政久もがんばってまいります!!
これからもどうぞよろしくお願い致します。
2012年11月08日
オバマ大統領再選後
こんにちは、みやざき政久です。
アメリカ大統領選挙、オバマ大統領が再選されましたね。
再選後の次期政権では、クリントン、キャンベルが交代しますから、対日政策を担当するスタッフがどうなるかしっかりみていきたいと思ってます。
それと、あれだけの中傷合戦して、ホントに国民融和できるのだろうか?
これも関心持ってみていきます。
アメリカ大統領選挙、オバマ大統領が再選されましたね。
再選後の次期政権では、クリントン、キャンベルが交代しますから、対日政策を担当するスタッフがどうなるかしっかりみていきたいと思ってます。
それと、あれだけの中傷合戦して、ホントに国民融和できるのだろうか?
これも関心持ってみていきます。